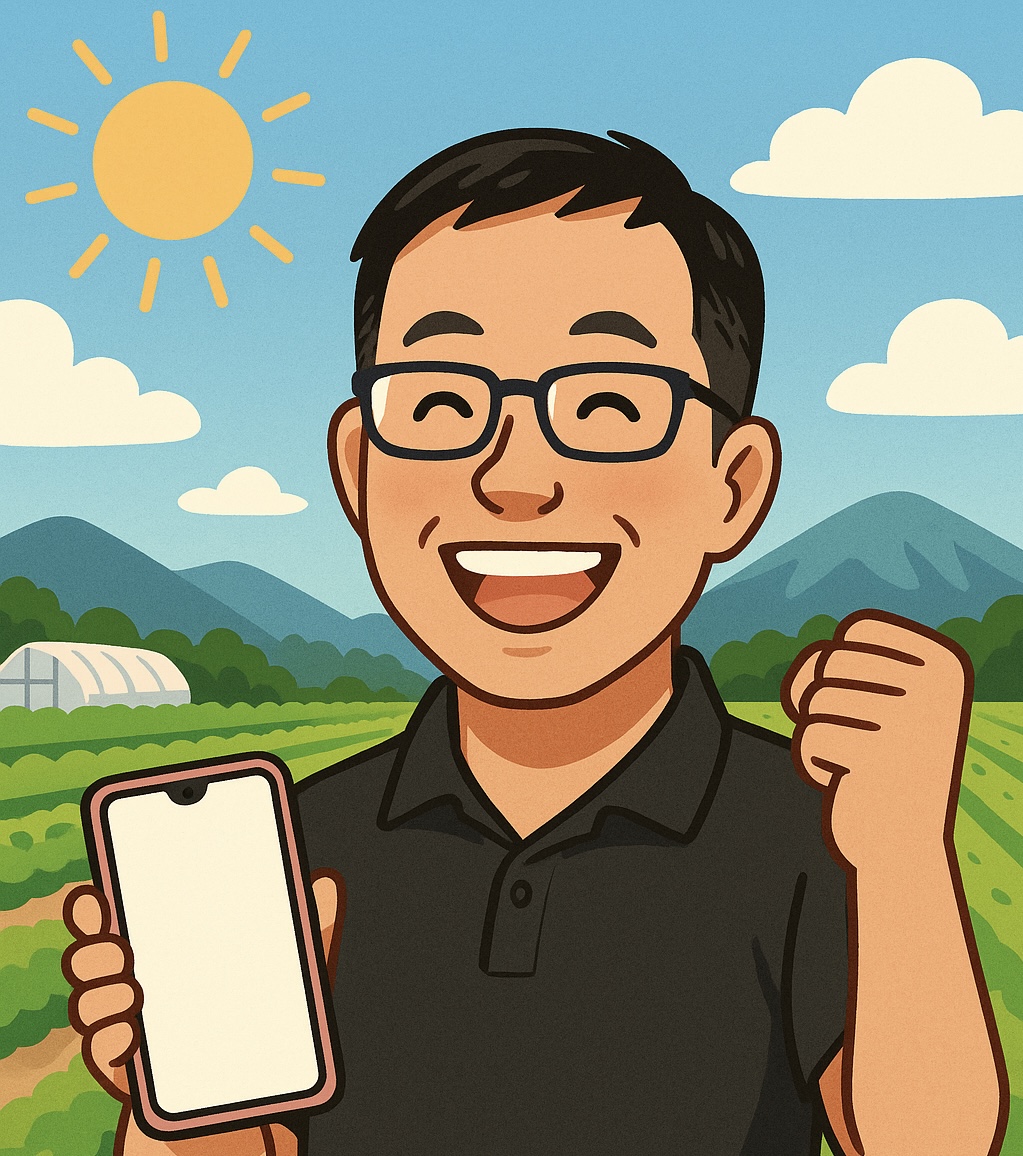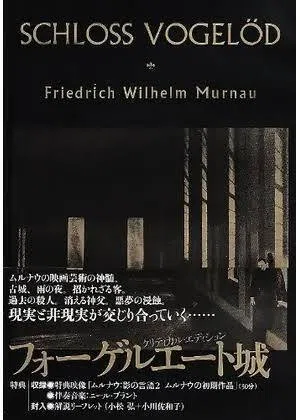
映画評「フォーゲルエート城」(1921年/ドイツ)
1921年/ドイツ/70分 監督:F・W・ムルナウ 撮影:フリッツ・アルノ・ヴァグナー 原作:ルードルフ・シュトラッツ 脚本:カール・マイヤー 出演:アルノルト・コルフ/ルル・キューザー・コルフ/ロータル・メーネルト/パウル・ハルトマン/パウル・ビルト
今見ると、カメラの質もセットも悪く、人形劇のようでもあり、さまざまな撮影手法が開拓される前の時代でもあり、独特の見た目の面白さがある。話はサスペンス要素があってなかなか興味深かった。殺人の容疑、招かれざる客、謎の失踪、驚きの真相。全5幕の中で、上手に話を展開していって、結末部分への興味がわくように作っている。第1幕ではなかなか難しい状況説明を試みている。エーチュ伯爵は見た目が悪者だ。非常に怪しい。嫌疑をかけられてもしょうがないような雰囲気だ。いいキャスティングだ。冒頭から「招かれざる客」の雰囲気がよく描けている。細かい人間関係は、極端なまでの説明セリフで解決しているが、当時の映画化を考えると、難しい脚本だ。殺された夫の妻、殺しの嫌疑をかけられた人物、何十年ぶりかで帰国する人物。閉ざされた空間での修羅場の前兆が描かれていて、物語の興味をそそられる。第2幕では一転して明るい狩りの雰囲気。馬に乗り、鉄砲を手に出発。子供や犬と一緒に2人の女性も戸外を走る。その雰囲気の中、狩りに出かけないエーチュ。さらに、なぜ夫はあんなに静かなのか問われて暗い表情をする女性。その明るい雰囲気と反比例するかのように暗い一瞬が上手に描写されている。苦悩する男爵夫人を演じるオルガ・チェーホヴァは、大根役者に見える。ただ、モスクワで演劇の教育を受けた経歴があるので、この時代の演出がこういう種類のものだったのかもしれない。事件の前触れ、隠された秘密。そして雨が降る。嵐の中、エーチュが狩りに出かける。明らかに異常な行為。不自然さが強調される。もっと不自然さを強調する撮り方も、今だったらあるかもしれない。壁にもたれて考える男の雰囲気がなかなかよく撮れている。夜。闇の中から馬車でやってくる神父。このシーンは真っ暗でよくわからないが、独特の雰囲気がある。城内ではくつろいでいる女性と心ここにあらずな表情の女性の対比。本来であれば待ちに待った人物と会えるのだから、もっと喜びがあってもよさそうなものだ。不自然なシーンをここに描くことによって好奇心をあおっている。そしていよいよ神父が到着。頭がはげ、眼鏡をかけ、長いひげを生やし、法衣を着て、個性豊かな外見である。かなり違和感があり、少し笑える。そして、苦悩する女性と神父の対面。ここが物語の一つのクライマックスだろう。第3幕では女性の告白。幸福を表現するシーンが興味深い。晴れていて、湖が見えて、花瓶に花を差す。そして夫が帰ってくるのが見えて、外に出て抱き合う。これが幸せの表現となる。とても素朴な表現だ。聖典に没頭する夫のシーンが印象的。光線を取りいれて良く撮れている。帰宅後、なぜ夫は豹変したのか。全くこの映画ではその理由が描かれていなかった点が気になったが、映画の流れとしては謎を提示していて興味深い展開だ。女性は、ここでなぜか話を打ち切る。ちょっと不自然な気もしたが、観客に謎を提示している。そして突然消える神父。城内の動揺を長く描いている。エーチュが神父を殺したのでは、と疑う客。この客のセリフが緊張感をあおっているので、シナリオ的には上手だ。厨房の少年の夢が間に挟まるが、全く話の筋とは無関係で、これはシュールで面白い。神父に生クリームをたっぷりもらいながら、給仕の頬を張り手しつづける。動きがなくて退屈だからこういうシーンを入れたのかもしれない。ただ、明らかに緊張感をそいでいるので、必要ないシーンだったかもしれない。第4幕になって物語が急転する。イスにもたれてネクタイを引っ張る男爵の苦悩の演技が非常に秀逸だ。一番見応えのあるシーンだ。クライマックスは多くの人物の前で指を差される伯爵。衝撃を与えて結末への興味を引っ張っている。第5幕では話がまとまっていく。通路の左に女性、右に男性が立っているシーンが素晴らしく魅力的だ。左右対称の芸術的な美しさだ。絵としてみても、光と影が強調されていて、非常に美しい。話としては、劇的要素を伴った非常に面白い結末だった。これを見るかぎり、ムルナウ監督には、サイレント映画にとどまることがないような才能のほとばしりを感じる。ただ、サイレント映画という枠組みの中で、上手に表現しようとも思ってない独特の才覚を感じる。今これを撮る場合は、もっと最後の謎解きの部分に趣向を凝らさないと単純すぎてつまらない映画になってしまう。時代が早すぎたのか、それともこれでよかったのか。永遠の謎を秘めた興味深い映画だった。