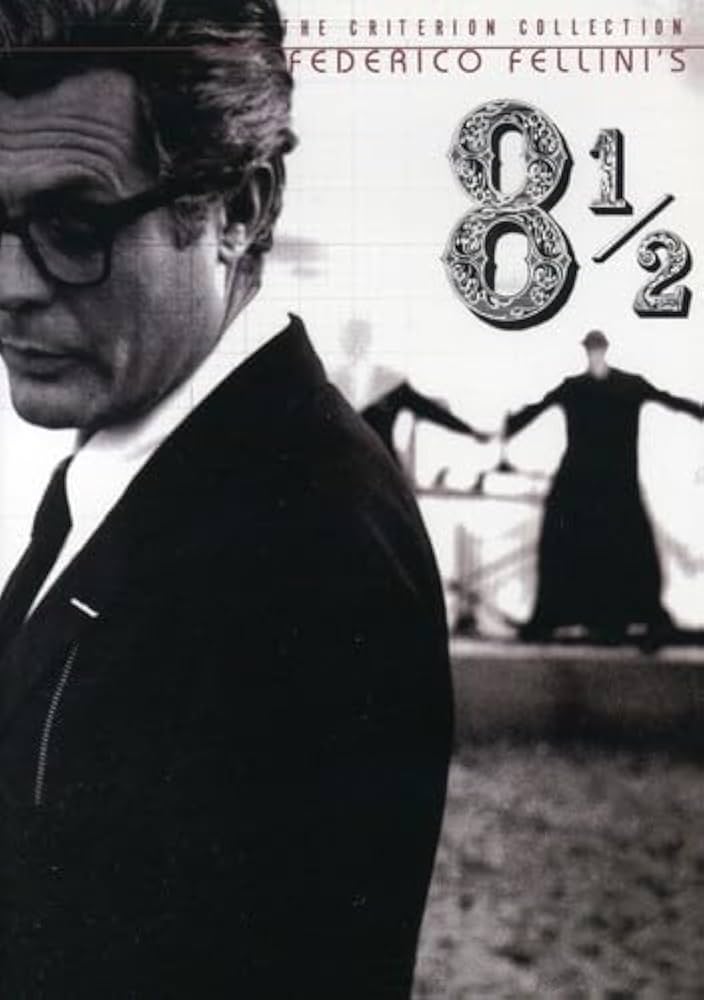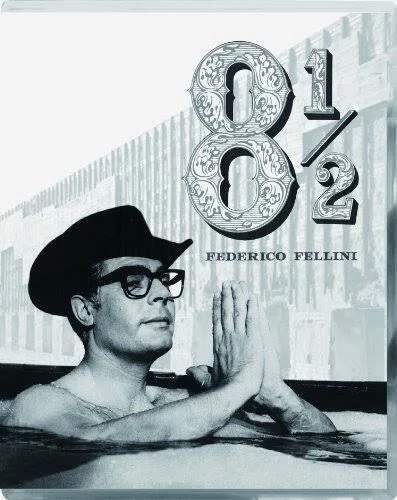
映画評「8 1/2」(1963年/イタリア・フランス)
1963年/イタリア・フランス/132分 監督・脚本:フェデリコ・フェリーニ 脚本:トゥリオ・ピネッリ/エンニオ・フライアーノ/ブルネッロ・ロンディ 製作:アンジェロ・リッツォーリ 音楽:ニーノ・ロータ 撮影:ジャンニ・ディ・ヴェナンツォ 出演:マルチェロ・マストロヤンニ/アヌーク・エーメ/クラウディア・カルディナーレ/サンドラ・ミーロ/バーバラ・スティール
渋滞、空を飛ぶ夢、足にロープ、転落。始まりからすでに混乱し、夢と現実を行き来している。映画と夢と現実が、強固に結びついている。スクリーンに写っているものは、映画でもあり現実でもあり夢でもある。明確な線引きは必要ない。はじめからなにかの実験であるかのように。人々に夢のすばらしさ、現実のすばらしさ、映画のすばらしさを伝えている。目の前に起きている状況が混乱している。私自身の意識もこの映画と同じように混乱しているので、この内面描写は自然だ。混乱している自分を、混乱していると理解している状態。作り手による客観視が行われている。論理的かどうかを判断する基準は、私の場合は意識の混乱が分かるので、突きつめてみると、あいまいだ。非論理的要素にも寛容であるべきなのだろう。ただ、観客にとっては、映画を見に行くこと自体、教会に行くかのような作業なのかもしれない。自分に持っていない絶対的な論理や絶対的な価値観を提示された方が観客は喜びそうだ。しかし、この映画では、とらえどころのない、ありのままの人間を、大胆にそのまま提示している。現実に追いつめられた人間が、甘い夢を見る。新作の脚本が書けない。未来をイメージできない。よってベクトルは過去に向かう。懐かしいイメージ。様々な女。不思議な呪文。映画監督が主人公。達観しているわけでもなく、人生観も定まらず、芸術観も定まらず、混乱している。混乱していたら映画など作れそうもないし、事実、主人公は苦闘している。しかし、その苦闘を描くことによって「8 1/2」という映画が完成されている。私小説のような映画。自らを客観視している点がすごい。自己防衛したり正当化したりしないところがすばらしい。作家が登場人物として映画に現れて、監督に批判的な言葉を投げかける。この、ロミエという男の存在が、大きな役割を持っている。監督を主人公としつつも、絶対的な権力や価値観を持たせてはいない。ロミエは、グイドの作る映画だけではなく、フェリーニ自身の映画にも批判の矢を向けているようにも見える。彼がいることで自分自身を客観的に描くことができ、等身大の人間としてグイドが存在できている。この人物配置は、共同脚本でもたらされた成果であるように見える。フェデリコ・フェリーニ、トゥリオ・ピネッリ、エンニオ・フライアーノ、ブルネッロ・ロンディ。この映画はフェリーニ独自で導きだしたのではない。彼らとの共同製作による所が大きい。さまざまな要素を分析しつくしている。しっかりした内面分析と、明晰な構造がある。作りこまれた迷宮のような多面世界でありつつも、しっかりとした実感がある。さらに、結末において全ての理性的な側面を軽々と越えてしまって、別次元に飛んでいる。私小説とは違って、主役が多重構造になっている。この映画を撮っている監督と、映画の中で主役を演じる監督が存在している。さらに、主役が撮ろうとしている映画の中での監督もいるかもしれない。そしてそれぞれが夢を見て空想を見ているようだが、実際のところ、空を飛んでいるのは、ハーレムで生活しているのは、輪になってダンスしているのはどの監督の夢なのか、よく分からない。空想と現実をありのままに描いている。そして、人生賛歌に終わる。この映画以外に、それを成し遂げた映画は少ない。突きつめていったら花が開いてしまったようなラストの踊り。不条理でもなく、不自然でもなく、映画の文脈では自然に見える。映画の可能性を押しひろげている。ストーリーは簡単だ。映画監督が実際に台詞として語っている。「主人公は我々と同じくカトリック教育を受け、あるコンプレックスを抑制できずにいる。枢機卿が現れ真実を示すが、彼は納得できずに、救いとなる゛ひらめき″を求める」これほど分かりやすい説明はない。孤独に書き続ければなにかが生まれてきたのかもしれないが、なにもひらめかないまま、人々がどんどん集まってくる。華やかに見えつつも恐怖だ。愛人、制作者、役者、妻。騒がしくなり、療養どころではなくなる。追いつめられた状態だ。期待されているので、その期待に応えなければならない。期待される状態に私はなったことがないのでよく分からないが、たくさんの人々が動き、たくさんの資本が動き、その組織の頂点に位置する者に全く意欲がないのはまずい状態だということは理解できる。あんなに巨大なロケット施設を作っておいて、実はなにもアイデアがない、と開き直るのはかなり難しい状態だ。「今、頭は混乱でいっぱいだ」健康な人間がこういう発想をするかというと、それは無理だと思う。圧倒的な断定口調ではなく、全編において悩んでいる。自信がない。存在が消えてなくなりそうなほどの無力感が漂う。「冷酷な論理と明晰さも必要だ。失礼ながら、貴方の無邪気さは重大な欠点だ」、「まさに混乱と曖昧さの極みだ」と劇中で監督は批判される。「何も語ることがない。だが語りたい」苦悩するドラマチックな自分に気づいた瞬間、おそらく目の前が開けたはずだ。ブレイクスルーの予感と自己陶酔。気高き自己肯定。サラディーナの回想は、カトリックへの違和感だけではなく、かつて否定された物の中に価値観を見つけたことも表現されている。自然そのものを愛する気持ちに気づいた瞬間だ。目の前の枢機卿よりもサラディーナの幻影の方が重要。枢機卿の背後に神ではなく彼女が現れる。彼女にひざまずき帽子を振り、彼女は振り向いて「チャオ」と微笑む。自己肯定への第一歩だ。温泉療養所が舞台となっている。病気を癒す場所だ。癒しの雰囲気が映画の中にある。温泉だけではなくて、映画撮影そのものがセルフヒーリングの手段になっている。温泉に浸るように映画に浸っている。「撮影療法」とも言えそうだ。自己を再生しながら映画も完成してしまっている。監督が主人公なので、ドキュメント映画のような、ノンフィクションのような、説得力がある。その自己肯定へのプロセスを観客も体感できてしまう部分が斬新だ。この映画を見ると、自然と自分の人生を肯定できてしまう。温泉の素のような、薬のような、人々をポジティブな気分にさせてしまうすばらしい効果がある。年を取り、疲れていればいるほど効き目がある。なにも起きない日常を描きつつも、カメラだけがどんどん動く。カメラが過去と未来を、現実と非現実を、自由自在に移動する。獲物を捕らえるかのように対象を外さない。まるでカメラそのものが生き物のようだ。饒舌な画面構成。早口でまくしたてるようなイメージの乱反射。人物の心の動きと連動した、激しい光と影。ジャンニ・ディ・ヴェナンツォはすごい撮影能力を持っている。ハーレムのシーンが最高だ。それぞれの女性の表情や物腰が、めくるめくように照らしだされていく。計算しつくしたとしても、ここまで流れるように描ききれるものなのだろうか。真珠を落としながら踊り娘が踊るシーンでは強烈な光と影が舞う。女たちは食卓に集まるが、妻が一人、床を掃除する。勢いがあり、活気がある。そして最後に悲しみが残る。楽しいのではなく、悲しい。全てが印象的な女性だけの家だ。カメラテストと客席の人々の切り替わりが激しい。感情の激しい動きを、巨大なスクリーンを使って表現している。暗闇に監督は一人。映画内映画の状況を効果的に使っている。最後にクラウディアという女優に会う。絶対的な美の象徴。人間を越えている。美しすぎて怖い。女神でもあり、愛人でもあり、主演女優でもある。全てを支配する存在だ。生命を支配しているようにも見える。死神のようにも見える。「全てを捨てて人生をやり直せる?」と彼は聞くが、すでに結論は見えている。捨てることなどできないのだ。「僕はここが大好きだ」彼はついに結論づける。その後の会話がすごい。「私の役はないのね」「そのとおりだ。君の役はない。映画もない。どこにも何もない」ここで、この私の鼓動が止まり、この映画が生命を持つ。決意の表われ。さらに生きていくための勇気。追いつめられて、監督は死ぬ。生か死か。それは映画の中で実際にあったことなのか、それとも主人公が撮るべき映画でのシーンにすぎないのか。もはや、そういったことさえも、ささいなことだ。主人公が撮るべき映画が消え、主人公が消え、私たちが見ている映画も最後には消えている。驚くべきことに、完全に世界が消え去っている。ここで私たちが目にしているのは、どういうシーンなのか。記憶がいつまでもそこにある。まだそこで生きている。ここで見ている我々も、生きている。そして監督も、生き生きとしてみんなと共に輪の中に入る。私たちも輪の中にいる気がする。自分を許し、認める。他人を許し、認める。共に過ごそう。一緒に踊ろう。どこかでなにかが起きている。そこは曖昧で混乱した世界だ。ここも同じだ。だから楽しい。だから美しい。映画が終わり、客席が明るくなる。私自身の心に帰る。心はまだ暗闇のままだ。心の暗闇の中で、目の前のスクリーンではまだこの映画が上映されている。暗ければ暗いほどこの映画のスクリーンは明るく照らしだすような気がする。よく見えるような気がする。それほど大きなプレッシャーはないが、私自身も私自身の人生に関するシナリオが作れない状況だ。様々な場所で行き止まりも多くなっていく。交通渋滞に巻きこまれ、車内が煙に満たされて、息苦しい人生だ。苦悩というものは、凡人であればあるほど多くなるはずだ。私の苦悩は、かなりの数だ。次の物語を発見できない苦悩は、多くの人々にあてはまる普遍的なテーマだ。そうそう何度もひらめきを起こせるものではない。8個も映画を作っていれば当然のことだろう。しかもフェリーニの場合、すでに世界的に認められている映画ばかりなのだ。天才の苦悩はそれだけでひらめきの元となるのか。しかもこの映画の場合、希望を感じさせるラストが用意されている。破滅ではなく、再生を感じる。なにか、とても良いことが起きている。もちろんこれは映画なので私自身に直接のひらめきをもたらすことはなく、ただ見ているだけにすぎない。しかし、美しいものは私を感動させる。見た目ではなく、心だ。サッカーのフリーキックで見事なロングシュートを決めた時のような、ディフェンダーやキーパーをすり抜けて見事な軌跡を描いてボールがゴールに吸いこまれていくのを見るような。心の美しい軌跡を眺めているだけで、勇気づけられる。フェリーニにはできたのだ。私にもそんな奇跡が起きるのではないか。ありのままの、あいまいで混乱している自分を受け入れること。「人生はお祭りだ。一緒に過ごそう」全員で手をつなぎ、自分もその輪の中に入る。どうだろう。そんな境地に私はたどりつけるだろうか。私たちに、そんな瞬間が訪れるだろうか。フェリーニはその後も元気に映画を作りつづけた。私にこれほどのひらめきが訪れるとはとうてい思えないが、少し気持ちが楽になった。