
(短編小説)ぼんやり猫探偵と消えたマタタビ(前編)
第一章 事件の予感
ある晴れた午後、クロスケはいつものように中学生のハナの膝の上でうたた寝を楽しんでいた。窓の外では小鳥たちが賑やかにさえずり、春の陽気が部屋いっぱいに満ちている。平和な時間だ。その時、玄関の呼び鈴が鳴った。ハナの母、ミッツさんが応対に出ると、驚きの声が上がった。
「はあい。あら、店長さん?」
「クロスケさんは、いらっしゃいますか?」
店長さんの声が少し緊張しているように聞こえた。「はいはい。クロスケですね?どうぞこちらへ」
ミッツさんが店長さんをリビングに案内する。ハナの膝の上で目を覚ましたブリティッシュショートヘアのクロスケは、店長さんの姿を見て小さく鳴いた。クロスケはうっすらと店長の顔を覚えていた。
「にゃあ?」
「あら。スーパーの店長さん?今日はどうしたの?」
ハナが不思議そうにたずねる。
「あの。うわさを聞きまして」
店長さんは言葉をにごし、クロスケをじっと見つめた。
「ああ。変なうわさが流れてることは知ってるわ。でも、あれはでたらめよ」
ハナは少し困った顔をした。
「とはいえ、誰も頼る当てがなくて、困ってるんです。話だけでも聞いてください」
店長さんは真剣な表情で訴えた。
「分かりました。同じ猫好き仲間として、お話を聞かせてください」
ハナはうなずいた。店長さんは深呼吸をし、クロスケに向かって話しはじめた。
「実は、我が家の看板猫のミミが、行方不明になったんです」
「まあ!あのシャム猫の?」
ハナが声を上げた。ミミちゃんは近所で有名な美猫だった。
「はい・・・」
店長さんの声は沈んでいた。
「なにか手がかりみたいな物はないんですか?たとえば、ミミちゃんが普段つけているものとか」
とハナが聞く。
「そうですね。ミミちゃんはふだんからキラキラ光るピンクの猫砂を使っていました」
「キラキラ光る。ピンクの猫砂だって」
ハナがクロスケの眉間をマッサージしながら声をかける。クロスケは心配そうに目を細めた。ミミちゃんはクロスケの友達だった。散歩コースにそのスーパーがあって、ミミちゃんには何度も店の魚をごちそうになっていた。自分にとっても大事件だ。
「にゃあ。ミミ・・・いない。どこへ行ったんだろう・・・」
いつもはぼんやりしているクロスケの心に、小さな火が灯った。彼女の美しい青い瞳と、しなやかな体が目に浮かぶ。クロスケは、ミミちゃんを見つけ出したいとぼんやりと思った。

第二章 路地裏の情報網
深夜。薄暗い路地裏に、ほの白い月明かりが差しこむ。いつものように、猫たちが集う猫広場は、今夜も様々な鳴き声でにぎわっていた。クロスケは仲間たちにのんびりと挨拶していく。
「やあ、ココ。今夜はいい月だね」
ベンガルのココは、少しゆううつそうに返事をする。
「そうね。でも、なんだか物足りないのよね」
「物足りない?なんだい?」
クロスケは首をかしげた。茶トラのチャチャが口を挟んだ。
「ココ姉さん、またマタタビのこと考えてるんだろ?」
ココは大きくため息をついた。
「ええ。最近、町からマタタビがすっかりなくなってしまったみたいなの。どこを探しても見当たらないのよ」
周りの猫たちも、ミケの言葉にうなずきはじめた。白黒のブチは、不安げにヒゲをふるわせながら言った。
「そういえば、このまえ、お気に入りのマタタビ畑に行ってみたら、きれいに刈り取られて更地になってたんだ。一体誰が・・・」
子猫のシロは、きょとんとした顔でココを見上げた。
「楽園?マタタビってそんなにいいものなの?」
ココは優しい顔でシロをなでた。
「ええ、シロちゃん。マタタビは私たち猫にとって、この世で一番素晴らしい贈り物なのよ。あの香りをかぐだけで、幸せな気分になれるし、元気も出る。まるで夢の中にいるみたい」
チャチャは残念そうに付け加えた。「最近は、その夢も見られなくて、みんな少し元気がないんだ」
「そうか。大変なことが起きているんだね」
とクロスケは目を丸くした。マタタビよりもマグロの方が好きだったけど、みんなの心配そうな表情を見ると悲しい気分になってきた。その時、壁の上から猫の影。
「ぐわっはっはっは!あーはっは!クロスケ!おぬしの活躍はわしの耳にも入っておるぞ!」
聞き覚えのある、甲高い笑い声が響く。ラパーマの猫仙人だ。長い白ヒゲを風になびかせ、宙に浮いているかのような軽やかさでクロスケに近づいてきた。
「こんばんは、仙人様。この機械をもらってから、なんだか僕、とっても忙しいんだ」
クロスケは首輪に付いた人間翻訳機を前足で軽くたたいた。この機械のおかげで人間の言葉が理解できるようになったのはいいが、様々な事件に巻きこまれるようになってしまった。
「引き続き、人知れず、猫知れず、良きことをするのじゃ」
仙人は目を細めてうなずいた。
「わかりました。あのね、仙人様。今日はスーパーのミミちゃんのことで来たんです。ミミちゃんが行方不明なんだ」
「ふむ。シャムのミミか。それは一大事じゃ」
仙人の顔が真剣になった。
「誰かミミちゃんのこと知らない?」
クロスケが周囲の猫たちに問いかけるが、みんなが首を横に振る。不安がクロスケの胸をよぎる。
「そうか。みんな知らないのか。情報屋のミケなら、なにか知っているかもしれない」
「おや、どうした?もう帰るのか?おい、今日はおぬしだけのために用意した特別のスーパー猫飲料があるんだが、興味ないか?今なら安くしてやるぞ」
猫仙人の提案にクロスケは思わず足を止めた。スーパー猫飲料。どんな味がするのだろう。
「仙人様。・・・また来ます」
スーパー猫飲料の誘惑を振り切り、クロスケが猫広場を出たとたん、路地裏から情報屋のミケが現れた。でも、今日はいつもと様子が違う。辺りを警戒するようにキョロキョロと見回している。
「ミケ、猫広場にいなかったのは、どうして?」
クロスケがたずねた。
「しっ!静かに。あそこにはスパイもいるかもしれない。今度の相手は大物よ」
ミケは声をひそめた。
「大物?」
「私、見たわ。ミミちゃんを。ピンクのバンに乗せられて」
ミケが真剣なまなざしで言った。
「ピンクのバン?なんだいそれ?」
クロスケは首をかしげた。
「車よ。車。人間によって連れ去られたのよ!」
「ふーん」
「人間が関わっているのよ」
「その人間は、どんな感じ?」
ミケは少し考えてから言った。
「そうね。少しネズミ臭かったわ」
ネズミ臭い?クロスケは眉をひそめた。一体どういうことだろう。ミミちゃんの行方不明に、人間とネズミが関わっている・・・?謎は深まるばかりだった。

第三章 マタタビ強盗団
路地裏の奥、錆びたトタン屋根の下。ひっそりと身を寄せ合う野良猫たちの吐息が、白い煙となって夜空に溶けていく。クロスケは壁に張り付き、息を殺して彼らの会話に耳を澄ませた。そのうち眠くなって、寝てしまった。夢の中ではたくさんのマグロの握り寿司が空を飛び、クロスケの口に吸いこまれていく。ウトウトしながらも、周囲の猫の言葉がクロスケの耳に流れこんでくる。
「またマタタビ強盗団が動いたらしいぜ。高級マタタビが根こそぎ消えたってよ」
「マタタビ強盗団って、ピンクのバンの連中か?」
「そうだ」
「なんてこった。世界中から全ての高級マタタビをなくすつもりなのか」
「盗まれるのは高級マタタビばかり。やつらの狙いは一体なんだろう」
やせこけた黒猫の声は、かわいた木の枝がこすれあう音のようだった。
「あのピンクのバンを使うってうわさは本当なのかい?」
クロスケは思わずつぶやいてしまった。黒猫は鋭い眼光をクロスケに向けた。
「なんだ、おまえは?ただのバカ猫かと油断してたら、いろいろ知ってるな?こんな所になんの用だ?」
「ん?あのね、ミミちゃんを探してて」
クロスケはたじろぎながら答えた。
「ミミ・・・あの美猫か?あいつもマタタビ強盗団にさらわれたってうわさだぜ」
灰色のトラ猫が低い声で言った。
「おや?」
クロスケは目を丸くした。黒猫が続けた。
「マタタビ強盗団は変異ラットを飼っている。マタタビ強盗団に近づいたら最後、生きては帰れねえ」
変異ラット・・・かつて人間に捨てられた実験用ネズミが、異常な進化を遂げたという恐ろしいうわさを、クロスケは思い出した。巨大な体と凶暴性、猫ですら襲われるという。
「ミミちゃん。ピンクのバン。マタタビ強盗団。変異ラット・・・」
クロスケはつぶやきながら、断片的な情報をつなぎ合わせようとした。でも、難しすぎてあきらめた。その時、一匹の白い猫が静かに口を開いた。
「待て。マタタビ強盗団は、ただの盗賊じゃない。彼らは、ある目的のためにマタタビを集めている」
「目的・・・?」
クロスケが問いかけると、白い猫は意味深に続けた。
「彼らは、マタタビを製薬会社に売ってるんだ。恐ろしい計画を進めているらしい」
白い猫の言葉はそこで途切れた。路地裏の入り口に、巨大な影が現れたのだ。人間の子供ほどの大きさの、変異ラット。鋭い爪と牙、赤く光る目。
「逃げろ!変異ラットだ!デカイぞ!」
黒猫が叫んだ。猫たちは蜘蛛の子を散らすように、暗闇に消えていった。クロスケもとっさに身をひるがえし、逃げ出した。背後から変異ラットの重々しい足音と、荒い息づかいが迫ってくる。心臓がはれつしそうになりながら、クロスケは路地裏を駆け抜け、なんとか追跡を振り切った。息を整えながら、クロスケは考えを巡らせた。ピンクのバン、変異ラット、製薬会社、マタタビ強盗団の恐ろしい計画。これらの点と点をつなぐ線を見つけなければ、ミミちゃんを助けることはできない。でも、ぼんやりしているクロスケにとって、この情報量は多すぎた。なんだか、とても眠くなってきた。
「そういえば、ピンクのバン。どこかで見かけたにゃー」
ふと、クロスケはピンクのバンに見覚えがあることに気がついた。近所の猫カフェで使っているバンだ。もしかしたら、強盗団と猫カフェはなにか関係があるのかもしれない。クロスケは確信した。次に目指す場所は、猫カフェだ。

第四章 猫カフェの異変
クロスケは、ピンクのバンが停まっているのを発見した。それは近所の評判の猫カフェ「にゃんドルハウス」の車だった。まさか、こんなところにミミちゃんが?クロスケは不思議に思いながら、カフェの裏口へと回った。半開きの窓から中を見ると、店内は荒れ放題だった。テーブルはひっくり返り、イスは倒れ、床には食べ残しのカリカリや、猫砂が散らばっている。そしてなによりもクロスケを驚かせたのは、壁一面に巨大なラットの足跡と、黒いフンがべっとりこびりついていたことだ。
「これは変異ラットの仕業かにゃー?」
クロスケは背筋を凍らせた。路地裏の猫たちの話が、現実のものとなったのだ。ここは、マタタビ強盗団のアジトのような気がした。ミミちゃんは、こんな恐ろしい場所に監禁されているのだろうか?クロスケは慎重に店の中に入った。あたりには、マタタビの香りがかすかに漂っている。床にはキラキラと光るピンクの猫砂。きっとミミちゃんの物だ。よく見ると、ピンクの猫砂で猫語が書かれてあった。
「ミミ・・・ここにいた・・・たすけて」
クロスケは胸が締めつけられる思いだった。その時、床の猫砂の中から、小さなピンクのリボンが出ているのに気づいた。ミミちゃんがいつも首に巻いていたリボンだ。クロスケはリボンを拾い上げ、ミミちゃんの匂いをかいだ。かすかに残る、ミミちゃんの甘い香り。黒い猫砂を背景に、ピンク色の猫砂でたくさんの花が描かれていた。ミミちゃんが描いたのだろうか?こんな花を、クロスケはどこかで見たような気がした。
「ミミちゃん・・・必ず助ける!」
クロスケは決意を新たにした。その時だった。ガタガタ!不気味な音が、奥の部屋から聞こえてきた。クロスケは音のする方へゆっくりと近づいていった。扉の隙間から中を見ると、そこには信じられない光景が広がっていた。数10匹の巨大な変異ラットが、床に散らばったマタタビの残骸をむさぼり食っていたのだ。体長はクロスケの半分くらいあり、鋭い爪と牙をむき出しにしている。
「あ。変異ラットだ。やっぱり、ここは、マタタビ強盗団のアジトだったんだにゃー。僕ってやっぱり名探偵だにゃー」
クロスケは夢見心地な表情で笑った。変異ラットたちは、一斉にクロスケの方へ振り向いた。ギラギラと光る赤い目。次の瞬間、変異ラットが襲いかかってきた。
「ぎにゃああああ!」
クロスケはカフェから逃げ出した。どうしよう。いつも仙人様は、
「わからなくなったら最初の出発点に立ち返れ」
と言ってたなあ。クロスケはぼんやりとミミちゃんが住んでいたスーパーに行ってみることにした。
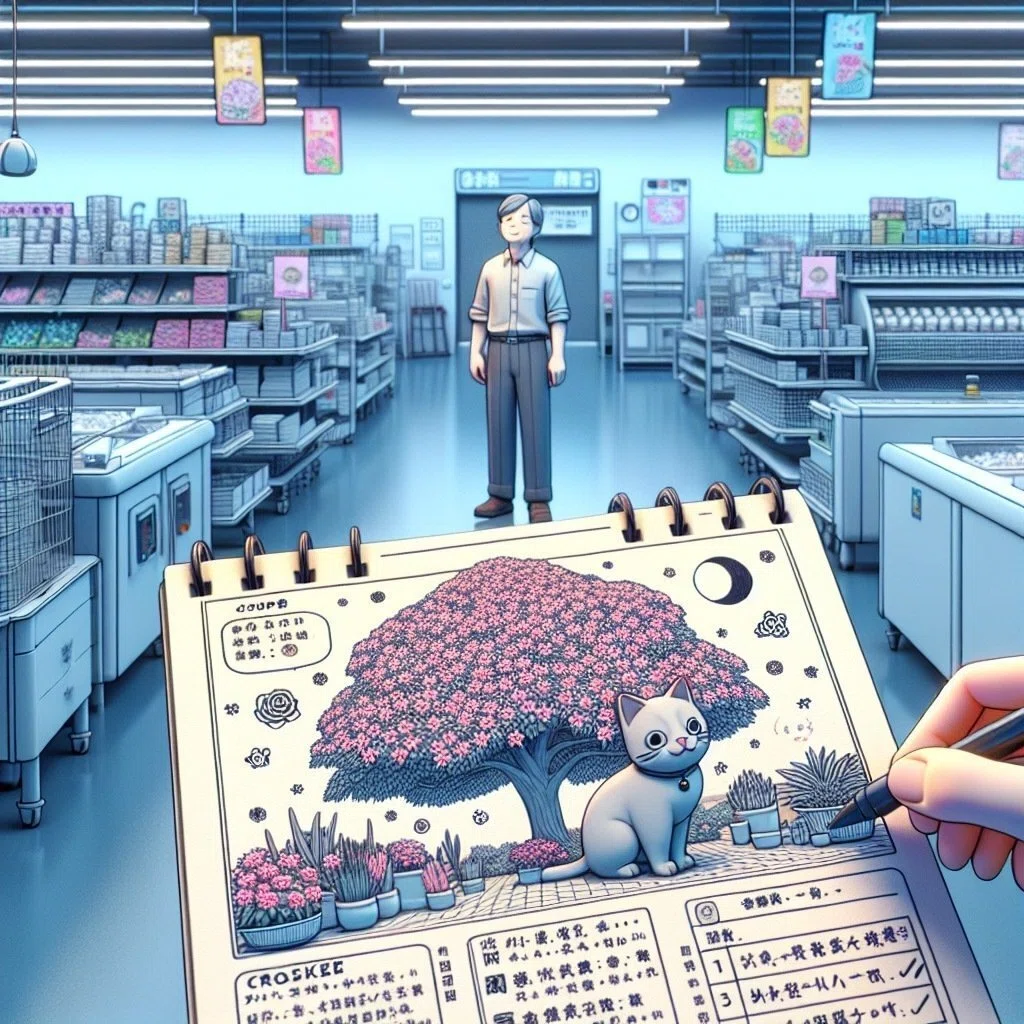
第五章 スーパーの秘密
クロスケはスーパーに到着した。いつも満員だったはずの店内は、人影もなくひっそりとしていた。店長は心配そうに店内を歩き回り、肩を落としながら奥の部屋に消えていく。クロスケは後を追う。
「はあ」
店長は机の前でため息をつき、頭を抱えた。
「おや?クロスケ」
と店長がクロスケを見つけて声をかけた。
「店長さん、どうしたの?」
クロスケは心配になって思わず人間語をしゃべってしまう。店長はびっくりした。
「とうとう幻聴まで聞こえはじめた。でも、ちょうどいい。人間には聞いてもらいたくない話を聞いてくれないかな」
「わかったにゃー」
店長の話によると、ミミちゃんは店の看板猫であるだけでなく、特殊な才能を持っていた。なんと、ミミちゃんがこの店で売る商品を決めていた。彼女の鋭い嗅覚と、人間の言葉の一部を理解する能力は、商品の品質を見極めるのに役立っていた。特に、魚介類の鮮度はミミちゃんのお墨付きがなければ店に並ばないほどだった。
「彼女のいない今、商品の仕入れができなくて。このままじゃこの店も倒産だ。ミミちゃんさえいてくれたらなあ」
店長はため息をついた。クロスケは、ミミちゃんのお気に入りの場所、レジの下に置かれていたメモ帳に気づいた。猫語でびっしりなにかが書かれていた。
「うわあ。スーパーで座っているだけかと思っていたのに。苦労してたんだにゃー」
「ほんとに、ミミちゃんには苦労ばかりかけてしまって」
店長がポロポロと涙を流しはじめた。クロスケはさらにメモ帳のページをめくると、ページ全部を使って大きな木の絵が描かれていた。大きな木には、ピンクの花がいくつも咲いていた。木の上には、大きな満月。猫カフェで見た絵とそっくりだった。
「あのね。店長さんの話を聞いてあげたから、僕の話を聞いてもらってもいい?」
「もちろん。なんの話だい?」
「あのね。僕は、1日に20時間くらい寝るし、たまに起きたら3日経ってることもあるんだ。僕だったら、この店の猫になりたくないにゃー」
「ええ?」
「だって。昼間も夜も、働くことになるでしょ?僕ね。今回の事件、全然なにが起きてるのかわからないんだけど、マタタビ強盗団よりも、ミミちゃんをずっと働かせてた店長さんのほうが、悪い人に見えるにゃー」
店長がそれを聞き、大粒の涙があふれ出てきて止まらなくなった。
「このメモを見てほしいにゃー」
店長は涙をぬぐい、猫語で書かれたメモを手に取った。もちろん読むことはできない。でも、ビッシリと埋めつくされた文字、所々に描かれた魚や肉のイラスト。ミミちゃんがどれだけ真剣に商品の選定をしていたか、その情熱が伝わってくるようだった。
「うん?これは?」
店長はメモ帳の裏表紙に貼られた小さなシールに気づいた。よく見ると、QRコードが印刷されていた。おそるおそるスマートフォンで読み取ってみると、画面にミミちゃんの写真とメッセージが表示された。
店長さん、いつもありがとう。私はスーパーのお仕事が大好きでした。でも、お店の売上のために、最近は悪い人と取引してしまいました。もしものときに備えて、ここに私の仕入れリストを書いておきます。新しい仕入れ担当が見つかるまで、これでなんとかしてください。
メッセージの下には、日付と、詳細な商品リスト、取引先のメールアドレスが記載されていた。店長はびっくりした。ミミちゃんは、自分が急に姿を消しても店が困らないように、ちゃんと準備をしていたのだ。
「ミ、ミミちゃん・・・」
店長の目から再び涙があふれて出た。今度は、後悔と感謝の涙だった。クロスケは静かに店長の肩にすり寄った。
「ミミちゃんは、店長さんのことが好きだったんだにゃー。だから、こんな準備をしたんだにゃー」
店長は深くうなずき、ミミちゃんのメモ帳を胸に抱きしめた。
「ミミちゃん、ありがとう。君のおかげで、この店は続けられる。必ず君を見つけ出して、今度は私が君を支える番だ」
クロスケはページの最後に書かれたメモが気になった。
「・・・マタタビ・・・お買い得・・・ムーンライト・・・特級品・・・危険・・・隠す・・・」
クロスケはメモの内容に目を丸くした。マタタビ?ムーンライト?店内のペット用品コーナーには、確かにたくさんのマタタビが並んでいた。でも、メモに書かれた「特級品」は見当たらない。一体どこへ消えたのか?そして、「危険」「隠す」とはどういう意味だろう?クロスケは店長の話をもう一度思い出した。
「最近、変わった商品は入荷した?」
店長は考えこんだ。
「そうだな。ミミちゃんが注文して新しいマタタビのサンプルが届いたんだが、それは倉庫に保管してある。まだ販売はしていない。それが特級品にあたるのかな?」
クロスケはピンときた。メモに書かれていた「特級品」とは、そのサンプルのことではないか? そして「危険」とは、そのマタタビになにか問題があるということかもしれない。ミミちゃんは危険なマタタビを誰かに知られないように隠したのか?クロスケは倉庫の場所を店長にたずねた。倉庫は店の裏手にあり、頑丈な鍵がかかっていた。店長は鍵を開けてクロスケを中に入れた。薄暗い倉庫の中、ダンボール箱が山積みになっていた。クロスケは鋭い嗅覚を頼りに、マタタビの匂いを追った。そして、ついに見つけた。奥の棚に、小さな木箱が置かれていた。「マタタビ・ムーンライト」と箱に書かれていた。中を開けると乾燥したマタタビが入っていた。でも、普通のマタタビとは何かが違う。強い香りが鼻を突き刺し、かすかに薬品のような匂いが混じっている。クロスケは思わずくしゃみをした。
「これは、一体・・・」
その時、倉庫の扉が勢いよく開いた。
「おまえたち、そこでなにをしている!」
怒鳴り声とともに、2人の男が飛びこんできた。1人はガラの悪い風貌で、もう1人は白衣を着ている。
「おお。そこに隠していたのか・・・」
ガラの悪い男がクロスケをにらみつけた。ネズミ臭い。この人たちが、マタタビ強盗団なのだろう。
「おい。そのマタタビをおれたちによこせ。邪魔をするな!」
クロスケは危険を感じてブルブル震えはじめた。
「クロスケ。ここは私がなんとかします。一刻も早くミミちゃんを見つけてください。お礼ならなんでもします」
「・・・マグロ」
そう言ってから、クロスケはとっさに身をかがめ、男たちの間をすり抜けて倉庫から飛び出した。
「待て!」
男たちが追いかけてくる。
「クロスケに手を出すなあ!」
店長が男たちに飛びかかった。乱闘が始まる。クロスケは全速力で走り、路地裏へと逃げこんだ。
「危ないところだったにゃー」
クロスケは息を切らしながら、路地裏の陰に隠れた。あの奇妙なマタタビ、ムーンライトの正体は?謎は深まるばかりだ。クロスケののんびりした頭では、どういうことなのか全くわからなかった。わからないので、猫仙人に聞いてみることにした。


