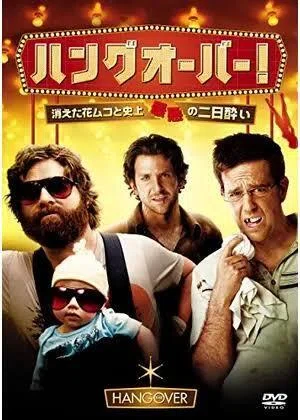(短編小説)ぼんやり猫探偵と消えたマタタビ(後編)
第六章 ムーンライト・ニャンタビ
いつもの猫広場。暗闇にほの白い月明かりが差しこみ、ひそひそと猫たちの声が聞こえる。クロスケは、不安な気持ちで猫仙人に相談した。
「お?ようやくおぬしのために用意した特別のスーパー猫飲料を買う気になったのか?」
「ううう・・・それも興味あるんですが、今はがまんしておきます。仙人様、ムーンライトっていうマタタビ、知ってる?」
猫仙人は長い白ヒゲを揺らしながら目を細めた。
「おお、聞いたことがある。ムーンライト・ニャンタビじゃ」
「ムーンライト・ニャンタビ?」
クロスケが目を丸くして聞き返すと、仙人は神妙な顔つきで語りはじめた。
「うむ。それはただの猫を酔わせるだけのものじゃない。特別な成分が含まれておってな。月の精気を浴びて育つ、珍しいマタタビじゃ」
猫仙人は感嘆の声を漏らす。
「え?どういうこと?」
クロスケは首をかしげた。猫仙人の言葉は、いつも謎めいている。
「ふむ、詳しいことは今は言えんが、いずれ分かる時が来るじゃろう。おそらく、ミミちゃんは、特殊な成分を持つムーンライト・ニャンタビを見分ける力があるのだろう。やつらはそれを利用するために誘拐したのじゃ」
猫仙人はほほ笑んだ。
「なるほど。さすが仙人様。ありがと」
お礼を言って、クロスケはゆっくりと広場の出口に向かう。すると、3匹の巨体が行く手を阻んだ。野良猫3兄弟、長男の茶トラのブチ、次男の黒猫ブラック、三男のサバトラのドットだ。
「あれえ?いつもは隣町の猫広場にいるよね。どうしてここに来たの?」
「おい、おまえ、もうこれ以上首を突っこむんじゃねえ」
ブチがクロスケをにらみつけた。
「この件から手を引け。さもないとどうなるか分かってるな?」
ブラックが鋭い爪を研ぎながら、脅すように言った。
「へっへっへ・・・へっへっへ・・・」
ドットは不気味な笑い声をあげた。
「気をつけて。あいつらはマタタビ強盗団の仲間よ」
情報屋のミケが現れた。クロスケは身構えた。
「僕はただ、ミミちゃんを探してるだけだ。邪魔をするなら・・・」
クロスケは低い声で警告した。しかし、3兄弟はひるむことなく、一斉にクロスケに襲いかかった。ブチは力強い猫パンチを繰り出し、ブラックは鋭い爪で切り裂こうとし、ドットは予測不能な動きでほんろうする。3匹同時に相手をするのは簡単ではない。クロスケはすばやい動きで攻撃をかわし、隙を見て反撃を試みるが、多勢に無勢。徐々に追い詰められていく。その時、背後から声が聞こえた。
「え?え?え?どうしてどうして。なぜスーパー猫パンチを使わないのじゃ?」
猫仙人だ。その姿に、3兄弟の動きが止まった。
「だって。・・・怖いんだ」
クロスケは正直に答えた。
「なにを怖がるのだ?」
猫仙人は不思議そうにたずねた。
「だって。スーパー猫パンチは回数制限があるって聞いたから。1日に4回使ったら、死ぬって本当?」
クロスケは真剣な表情でたずねた。猫仙人は真剣な顔でうなずいた。
「うむ。1日4回打ったら死ぬ!確実に死ぬ!」
「やっぱり本当だったんだ・・・。嫌だよ、そんなの。だって、猫パンチだよ?自分で止められないよ?勢いで何回もパンチしちゃったらすぐ死ぬじゃん」
クロスケは青ざめた顔で言った。
「落ち着け、落ち着け。わしは言ったじゃろ?良きことに使うのじゃと。自分の身を守るためにも、使っても良いのじゃ。それに、おぬしならできる!たぶん。しっかり数えて、しっかりと打つのじゃー!」
猫仙人はクロスケの肩をたたき、励ました。猫仙人の言葉に勇気づけられたクロスケは、意を決して首輪のスイッチを起動してスーパー猫パンチの構えをとった。3兄弟は恐怖におびえ、後ずさりした。
「ニャー!」
クロスケの拳から、まばゆい光が放たれた。3兄弟は光に包まれ、吹き飛ばされ、壁に激突し、気絶した。
「しゅ、しゅごい」
「やった!クロスケ!初めて打てたのね!」
情報屋のミケがクロスケに抱きついた。猫仙人が前足をたたいて踊りだす。
「でかした!」
クロスケがフラフラして尻餅をついた。ミケが抱き起こす。
「1発で、すごく疲れた。た、たしかに1日に3発が限界かもにゃー」
「大丈夫?」
「そうだ。ミケ、製薬会社って知ってる?」
ミケは目を見開いた。
「まさか、クロスケもあのうわさを聞いたの?」
「うわさ・・・?」
「うん、最近、猫界でひそかにささやかれているのよ。人間たちがマタタビを使って、とんでもないことを企んでいるって」
ミケはクロスケに1枚の紙切れを渡した。
「これが、その製薬会社の住所。でも、用心してね。そこは厳重に警備されているらしいわよ」
紙切れには「株式会社ニャンコライフサイエンス」という社名と住所が書かれていた。
「ありがとう。それで、製薬会社って、なに?」
「薬を作っているところよ。薬っていうのは、病気になったときにつける物よ。マタタビのような物」
「ふーん。教えてくれてありがとう。ミミちゃんを探しに行ってくる」
クロスケはゆっくりと製薬会社へと向かう。
「特別のスーパー猫飲料!人気商品!あと10本!」
猫仙人がクロスケの後ろ姿に声をかける。クロスケは立ちどまる。しばらくして、のそのそと歩きはじめた。
「よしよし。あとひと押しで、必ず買うぞ」
猫仙人が満足そうにうなずく。ミケが軽蔑した目で猫仙人を見る。
「やめなさいよ」
「それにしても、頼りない後ろ姿じゃ」
猫仙人が心配そうな表情を浮かべる。
「そんなクロスケに、なぜ仙人様は人間翻訳機とスーパー猫パンチをあげたの?私なら高く買いましたよ」
「おぬしは他の猫に売り飛ばすか、その力で悪さをするかもしれん。人知れず、猫知れず、良きことをするのが我がモットー。おぬしこそ、報酬がなければ絶対に情報を教えないくせに、なぜクロスケにはいつもタダで教えてやってるんじゃ?」
「私がいないと、あの子、心配でしょ?それに、とっても、のんびりしてるから。のんびりしてるくらいが、ちょうどいい気がするの」
のんびり歩くクロスケの後ろ姿を2人で黙って見つめる。

第七章 潜入!ニャンコバイオテック
次の日。町外れの丘の上に建つ近代的なビルを見上げるクロスケ。たどり着いたのは、製薬会社「ニャンコバイオテック」だった。
「まさか、こんなところに、ミミちゃんが?」
周囲を高いフェンスが囲み、警備員が巡回している。正面突破は難しそうだ。のんびりした自分には不可能に思えた。
「どうやって中に入ろう」
クロスケはビルの周りをぐるりと一周してみた。すると、裏手に積み上げられた空のダンボール箱を発見。どうやら搬入口付近らしい。
「これだ!」
クロスケはダンボール箱の陰に隠れ、警備員の巡回ルートを観察する。数分後、警備員が死角に入った瞬間、素早くダンボールの山に飛びこんだ。一番上のダンボールにまぎれこみ、息を潜める。ガラガラと音を立てて搬入口のシャッターが開いた。フォークリフトがダンボールの山に近づき、クロスケの乗ったダンボールごと持ち上げた。
「今のうちだ!」
フォークリフトが倉庫に入った瞬間、クロスケはダンボールから飛び降り、棚の陰に隠れた。倉庫内はとても広く、様々な物が積み上げられていた。クロスケは慎重に倉庫内を移動し、従業員の出入りするドアを見つけた。ドアの隙間から様子をうかがうと、廊下を歩く人々の姿が見えた。
「よし、潜入開始!」
クロスケはドアが開くタイミングを見計らい、素早く廊下へ飛び出した。そして、すぐに2人の警備員に見つかった。クロスケはのんびりしてたので、逃げ遅れてしまった。クロスケはもうあきらめて、どうでもよくなって、床にぐったりと寝そべった。
「あの猫、迷い猫ですかね?外につまみ出しますか?」
若い警備員が年配の警備員にたずねた。年配の警備員はクロスケをじっと見つめ、ニヤリと笑った。
「いや、あれは社長の猫だ」
「え?社長の猫?あんな見た目でしたっけ?」
若い警備員はいぶかしげな顔をした。
「あたりまえだろ。ただのノラ猫が、あんなにのんびりと会社でゴロゴロしているものか。それに、あの風格」
年配の警備員は意味深に言った。
「たしかに。この会社の社長みたいに堂々としてますね」
若い警備員も納得した様子でうなずいた。
「よし、そのままにしとけ。行くぞ」
2人はクロスケを気に止めることなく、向こうに去っていった。クロスケは幸い誰にも気づかれず、そのまま廊下の陰を進んでいく。社内は迷路のように複雑な構造をしていたが、クロスケはぼんやりしながらも、持ち前の運動神経と鋭い嗅覚を使って、ようやく目的の場所を探しあてた。
社長室と書かれた部屋の中で、太った男が電話で話しているのが見えた。クロスケは人間翻訳機を起動させ、会話に耳を澄ませる。社長が話している。
「・・・ええ、順調です。場所はあの廃工場。例の成分は、ムーンライト・ニャンタビの限られた種類から抽出できることが検証実験で判明しました。若返り薬『ネオ・ニャンティス』の開発も最終段階です・・・治験の許可も下りたので、すぐにでも・・・」
若返り薬?ネオ・ニャンティス?クロスケはなにかを感じたが、ぼんやりしているのでやっぱりよく理解できなかった。ムーンライト・ニャンタビから若返り薬の原料を抽出?盗まれたマタタビは、この人たちが使っていたようだ。
「ふむふむ、なるほど。猫を若返らせるのではなくて、人間を若返らせる薬?」
クロスケはぼうっとしながらも、大変なことが起きているような気がしてきた。その時、背後から声がした。
「おまえ、人間翻訳機を持っているな。なかなか面白いニャ」
振り返ると、そこに立っていたのは、長毛で優雅なラガマフィンだった。
「き、君は?」
「ラガマフィンの小次郎。ニャンコバイオテックの社長秘書兼、用心棒にゃ。ニャンコバイオテックの秘密を嗅ぎまわるとは何事だ!社長の計画を邪魔する者は、誰であろうと許さない!」
「ちょっと、いいかにゃ?」
「ん?なんだ?」
「あのね。どうしてこの会社は、マタタビ強盗団からマタタビを買い取ってるんだい?」
「社長の言ったとおりだ。マタタビ強盗団はマタタビをこの会社に高く売りつけて儲けている。そして、この会社は、そのマタタビを使って違法な実験をしているんだ」
「にゃ、にゃるほど。あとね、ミミちゃんのこと、知ってる?」
「ミミちゃん?ああ。あのスーパーの経営者のことか?もちろん知っている。この地球上でミミちゃんだけがムーンライト・ニャンタビを見分けることができる。ミミちゃんは自分で採ってきたムーンライト・ニャンタビをマタタビ強盗団に売っていたが、毎回買うのがめんどくさくなった強盗団に誘拐されたのだ。ミミちゃんを誘拐してからは、マタタビ強盗団も動きが派手になってきた。手当たり次第にマタタビを奪ってきては、ミミちゃんに調べさせて大量のムーンライト・ニャンタビを手に入れることができるようになったんだ」
「にゃ、にゃるほど!」
「この秘密を聞いたからには、生かしてはおけないニャ」
小次郎は不敵に笑い、戦闘態勢に入った。毛を逆立て、鋭い爪を立てる。小次郎は鞭のようにしなやかな尻尾を振るわせ、クロスケに襲いかかってきた。
「待って!もっと話を・・・にゃにゃ!」
クロスケは慌てて身をかわす。小次郎の攻撃は速くて正確だ。
「ぼ、ぼんやりしているくせに、動きが速いな!無駄な抵抗はよせ!ここで大人しく消えてもらうニャ!」
小次郎はさらに激しく攻撃を続ける。鋭い爪がクロスケの頬をかすめ、軽い傷がついた。
「ぬにゃにゃ!」
クロスケも反撃を試みるが、小次郎は簡単には捕まらない。まるで忍者のように、素早く動き回り、攻撃をかわしていく。
「ふふふ。無駄だニャ。私の戦闘能力は、社長直々に鍛え上げられたもの。虎よりも強い。おまえのようなぼんやり猫には、勝ち目はない!」
小太郎は口から弾丸を発射した。
「げほっ!なんだこれ?」
毛玉は見た目以上に硬く、クロスケの体に当たると、鈍い痛みが広がる。
「これは私の特製毛玉爆弾ニャ!くらえ!」
小次郎は次々と毛玉を吐き出し、クロスケを追いつめていく。
「痛い痛い痛い!」
クロスケは劣勢を強いられていた。小次郎の攻撃は容赦なく、スーパー猫パンチを繰り出すすきもない。体中が痛み、意識ももうろうとしてきた。でも、このままではマタタビも、みんなの未来も守れない。
「あきらめないニャ!」
クロスケは最後の力を振り絞り、小次郎の攻撃を紙一重でかわすと、床に転がった毛玉爆弾をまとめて大きな毛玉を作った。
「ニャにをする気だニャ!?」
驚いた小次郎に、クロスケは渾身の力で毛玉爆弾を投げつけた。
「くらえ!スーパー毛玉返しニャ!」
大きな毛玉爆弾は小次郎の顔面に命中。小次郎はよろめき、体勢を崩した。その一瞬のすきを逃さず、クロスケはついに奥義を繰り出した。
「ねこおぉぉっ!」
強烈なスーパー猫パンチの一撃が小次郎の腹部に炸裂。小次郎は悲鳴を上げ、遠くまで吹き飛ばされた。
「にょにょーん!」
グワッシャッ!
小次郎は壁に激突し、そのまま力なく倒れこんだ。クロスケはよろめきながら立ち上がり、勝利を噛みしめた。体は傷だらけだったが、なんとか勝つことができた。
「やったニャ・・・」
「ふふ。おれを倒したからと言って喜ぶなよ。ボスの方が圧倒的に強いからな。こ、この程度の猫パンチじゃ3発打っても倒れることはないだろう」
「ボスはどこにいるんだい?」
「は、廃工場に決まってるだろ。町外れの廃工場だ」
そう言って、小次郎は気絶した。
「廃工場。町外れ。どこにあるかわからないから、ミケか仙人様に聞いてみよう」
クロスケはぼんやりと毛づくろいをしはじめた。

第八章 廃工場の決戦
次の日、情報屋のミケから場所を教わったクロスケは町外れの廃工場に向かった。サビついた鉄の扉に、鋭い爪痕が無数に刻まれていた。廃工場の入り口だ。奥からは、かすかな獣の息づかいと、なにかがカチャカチャと動く機械的な音が聞こえてくる。クロスケは鼻をひくひくさせ、ミミちゃんの残したかすかな香りを追っていた。ピンクのバンのタイヤの跡も、ここまで続いていた。クロスケは廃工場へ潜入。抜き足、差し足、忍び足、猫足。狭い場所もしなやかに、高い場所も跳躍力で昇り降り。工場内部は薄暗く、巨大な機械の影が不気味に伸びていた。中にはたくさんの人間がいて、さまざまな機械の中にマタタビを入れて、ほのかに青白く輝く液体を作り出していた。スーパーで会ったネズミ臭い2人組も働いていた。埃っぽい空気に、油と薬と強いマタタビの香りが混じり合う。マタタビの匂いでだんだん眠くなってきた。
「しっかりするにゃー」
自分で自分に言い聞かせてクロスケは先を進む。床には、変異ラットの足跡と、ピンクのキラキラした猫砂が散らばっていた。
「ミミちゃんだ」
クロスケは確信した。奥へと進むにつれ、マタタビの香りが濃くなっていく。やがて、広大な空間に出た。そこには、山のように積み上げられたマタタビと、怪しげな装置。その前にロープで縛られたミミちゃんの姿があった。大きなドーベルマンが装置を動かしている。いくつものパイプが複雑にからみ合い、装置の中心部では、マタタビがなにやら怪しい液体に溶けこんでいる。
「グフフ。このマタタビから特別なエキスを抽出して、若返り薬の原料にするんだ!」
ドーベルマンが不気味に笑った。
「ミミちゃん!」
クロスケは叫んだが、ミミちゃんはクロスケを見てびっくりした。
「クロちゃん?早く逃げて!クロちゃんじゃボスには勝てないわ」
ミミちゃんが叫んだ。振り返ったドーベルマンが牙をむき出しにして立ちはだかった。
「グルルゥゥ・・・。侵入者か!」
ボスが体をふるわせて恐ろしい顔でクロスケをにらみつける。
「おまえがボスか!ミミちゃんを自由にしろ!」
クロスケが叫んだとたん、ボスがダッシュして犬パンチ。なんとかよけたが、パンチは床にぶつかり、大きな地割れが走る。さらにボスは犬パンチの連打。当たったら一撃で死んでしまいそうだ。クロスケはあわてて後ろに逃げる。
その時、天井のパイプが崩れ落ち、変異ラットの群れがクロスケに襲いかかってきた。鋭い爪と牙が、クロスケのに迫る。
「ニャーゴ!クロちゃん!後ろ!」
ミミちゃんが叫んだ。その声で、ボスが一瞬ミミちゃんの方を見たすきに、ロープが少し緩んだ。絶体絶命のピンチ。クロスケは首輪に前足をかけた。
「ねねねねっ!・・・あれ?」
スーパー猫パンチの構えを見せたが、変異ラットの数はあまりにも多い。スーパー猫パンチは回数制限がある。焦るクロスケ。その時、ミミちゃんが機転を利かせた。ミミちゃんが縛られていたロープから抜け出して、何度も大きくジャンプ。変異ラットたちの注意を自分の方に向けたのだ。
「ニャー!こっちこっち!醜いネズミども!」
ミミちゃんが挑発する。そのすきに、クロスケは狙いを定めた。深呼吸をして、渾身の力をこめて。
「ねこおぉぉっ!」
ドゴォン!
スーパー猫パンチが、変異ラットの群れの中心に炸裂!衝撃波が工場内に響き渡り、変異ラットたちが吹き飛ばされて空を飛ぶ。
「まだだ!ねこおぉぉおっ!!」
ひるむ間もなく、クロスケは2発目のスーパー猫パンチを放つ。床が揺れ、天井からゴミが舞い落ちるほどの衝撃。変異ラットたちは、ボスを守るようにして群がり、次々と倒れていく。でもボスはまだ立っていた。
「ワン!なかなかやるな、こしゃくな猫め!だが、これで終わりだ!」
ボスは傷つきながらもなお威圧感を漂わせ、クロスケに迫る。ボスは、びっくりするほどの速さで動いた。クロスケはかろうじて身をかわしたが、ボスの牙がクロスケの肩をかすめ、鮮血が飛び散った。
「イテテテテ!」
ボスはさらに攻撃の手をゆるめない。犬パンチの連打。強烈な一撃がクロスケの腹部に当たり、クロスケは吹き飛ばされて壁に激突した。息がつまり、全身が痛みで悲鳴を上げる。その巨体から繰り出される攻撃は、スピードとパワーが増しているかのようだ。絶体絶命のピンチ!
「ガハハハ!猫め!貴様のような猫がおれにかなうものか!」
ボスは勝ちほこったように高笑いする。クロスケは最後の力を振り絞り、首輪に前足をかけた。
「こ、これが、最後の、スーパー猫パンチ!」
よろめきながら立ち上がったクロスケは、ボスの巨体に狙いを定めた。
「ねこおぉぉぉおっ!!」
全身全霊をこめたスーパー猫パンチが、ボスの顔面に炸裂!
ドゴォォン!!
閃光が工場全体を包みこみ、爆風が吹き荒れる。ボスは吹き飛ばされ、壁に激突。でも、それでもボスは立ち上がり、爆風の煙の奥で、不気味な笑みを浮かべている。
「グフフ・・・これで終わりだと思うなよ」
「ギャ!ギニャアア!」
ボスが飛びかかってきた。もうすでにスーパー猫パンチを3発打ってしまった。あと1発くらいなら大丈夫かな?でも、猫仙人は「確実に死ぬ」と言っていた。逃げようかな。どうしよう。でも、ここで逃げたらミミちゃんも助からないし、マタタビも世界からなくなってしまう。クロスケは最後の最後で勇気を振り絞った。
「ねねねね!ねこおぉぉっ!」
ズッドドドドドォォォォォン!
ボスのアゴにクリーンヒット!スーパー猫パンチは廃工場全体を覆うほどの巨大なエネルギー弾となり、閃光が辺りを包みこみ、爆風が吹き荒れる。廃工場は砂の城のように崩れ落ち、跡形もなく消滅した。瓦礫の山からよろよろと姿を現すクロスケとミミちゃん。勝負あった。でも、3連発。思わず勢いでたくさん打ってしまった。本日6発も打ってしまった。クロスケはダメージが大きく、瓦礫の上にドサリと倒れる。ミミちゃんが駆け寄る。
「しっかりして」
「イテテテテ・・・あれ?生きてる」
クロスケは不思議そうにゆっくりと身を起こした。
「どうしたの?」
「スーパー猫パンチは、1日に4回以上打ったら死ぬはずなのに。僕、生きてる」
「あ!もしかして、今、0時過ぎたんじゃない?」
「え?日付が変わったから、次の日になったってこと?だから平気だったのか!」
クロスケはミミちゃんに駆け寄り、抱きついた。
「クロちゃん、ありがとう!助かったわ!」
「ミミちゃん、よかった!」
クロスケは安堵の息を吐いた。こうして、マタタビ強盗団の陰謀は阻止された。
クロスケとミミちゃんは静かに廃工場の跡地を後にした。夜空には、大きな満月が輝いていた。
「ミミちゃん。少し、ぼんやりしていこう」
2匹はしばらく無言で歩き続け、小高い丘の上にたどり着いた。丘の上には、大きな八重桜の古木。今まさに満開を迎えていた。たくさんのピンクのふんわりした花びらが集まって、丸くふっくらとした花束になって、夜空にどこまでも広がっている。
「ここは僕がよく来るところだよ。この場所で、昼寝したり、のんびりしているんだ。春は、昼寝の季節だ。のんびりいこうよ」
クロスケは、ミミちゃんにほほ笑みかけた。夜空に浮かぶ満月と、淡いピンク色の八重桜。満月の光を浴びて、花びらは一つ一つがほんのりと輝き、のんびり咲いていた。風に揺れるたびに、花びらはひらひらとゆっくり舞い落ちる。地面には花びらが桃色のじゅうたんのように優しく広がっている。ここは、猫カフェの砂場に描かれていた景色、スーパーのメモ帳に落書きされていた景色、ミミちゃんの心の中の景色。
「こんなにキレイな場所があったのね。お店の仕事が忙しくて、外に出たことがあまりなかったから」
ミミちゃんは、うっとりと八重桜を見上げた。満月の優しい光が、ミミちゃんの顔を照らし、その美しさをさらに際立たせている。
「キレイなお月様。4月の満月は、ピンクムーンっていうのよ」
「ピンク・・・?あっ」
クロスケは思い出すと、首輪の内側にしまっていたリボンを取り出した。
「落とし物だよ」
リボンをつけてミミちゃんが笑った。
「ありがとう」
「ミミちゃんも、たまには猫広場に来てね。面白い猫ばかりだから」
「うん」
ミミちゃんは静かにうなずいた。2匹は並んで八重桜の木の下に座り、満月を眺めた。


第九章 永遠の謎
スーパーの店長が家を訪れる。
「おかげさまで、ミミちゃんが帰ってきたよ。このたびは本当にありがとうございました」
「良かったですね。でも、クロスケは関係ないんじゃない?」
「いやいや。それがね。私の妻が庭で最初にミミちゃんを見つけたんだけど、一緒にいたのがクロスケだったというんだよ」
「へえ。ほんと?クロスケ」
クロスケが眠そうに鳴いた。
「最近はスマホで世界中の人としゃべれるけど、猫としゃべれる翻訳アプリがあれば、便利なのにねえ」
とハナがため息をついた。
「猫は永遠の謎だねえ」
と店長は言いながら、持っていたスーパーのビニール袋をガサゴソ開き、
「お礼の品だよ」
とクロスケに耳打ちした。大きな大きな高級マグロの大トロだ。いちもくさんに食べるクロスケ。ハナは高級マグロを見てびっくりした。
「わ、私もそんなマグロ、食べたことないよ。良かったね。クロスケ」
店長はしゃがんで、マグロに夢中なクロスケに声をかけた。
「私も反省したよ。今度は、私がほとんどの商品を仕入れているんだ。もちろんミミちゃんの時よりお客さんは少ないけどね。でも、がんばるよ。ペット用品と魚売り場だけは今もミミちゃんに任せてるよ。それがミミちゃんの生きがいだって言うからね」
クロスケはマグロを食べ終わり、満足そうに大きく鳴いた。
「にゃー!」
深夜、クロスケは路地裏を歩く。今夜はマタタビパーティだ。マグロを食べたことを、みんなに自慢しに行こう。ミミちゃんは来てるかにゃー。スーパー猫飲料もまだあるかにゃー。飲んでみたいにゃー。月の光が雲間からのぞく。新たな冒険の始まりだ。